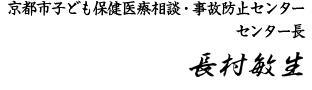理事長挨拶
理事長あいさつ
 このたび長村敏生先生の後を継ぎ、日本小児救急医学会の理事長を拝命いたしました井上信明と申します。小児救急研究会から始まった本学会は、すでに40年近い年月を重ねて活動を続けてまいりました。この伝統ある本学会において、多くの功績を残してこられた歴代の理事長の先生方の後を受け、このような重責を担うこととなり、身の引き締まる思いです。
このたび長村敏生先生の後を継ぎ、日本小児救急医学会の理事長を拝命いたしました井上信明と申します。小児救急研究会から始まった本学会は、すでに40年近い年月を重ねて活動を続けてまいりました。この伝統ある本学会において、多くの功績を残してこられた歴代の理事長の先生方の後を受け、このような重責を担うこととなり、身の引き締まる思いです。
近年小児救急医療を取り巻く環境は、新興感染症や自然災害への対応、少子化の加速、医療資源の地域偏在、そして医師の働き方改革による時間外労働の縮減など、さまざまな課題に直面しています。こうした状況の中でも、すべてのこどもたちが「根拠のある安全かつ安心な救急医療を受けられる体制」を維持・強化することが、私たちの使命であると考えています。
取り組むべき課題は多くありますが、まず小児救急医療を提供するために必要となる、人材育成には正面から取り組みたいと考えています。そのためには、小児救急医療をになう医療者のアイデンティティーの確立が必要です。本学会では、2019年に「小児救急医療の教育・研修目標」を作成しました。この目標は、職種や専門分野を超えたさまざまな立場の医療者、また保護者から聞き取ったニーズを基に、小児救急医療に関わる医療者に求められるコンピテンシー(能力)を提示しました。したがって、この教育・研修目標に沿った人材育成を進めることは、時代に求められる小児救急医療の担い手の育成につながります。またそれだけでなく、人材育成の持続可能性を確保するためには、小児救急医療の魅力と社会的意義を次世代に伝え、多様なキャリアパスを提示できるようにしていくことも必要です。
また、これからの医療は革新的技術の導入なくして進化はありません。特に小児救急医療の分野においては、AIを活用したトリアージ支援、情報通信技術を利用した遠隔診療システム、シミュレーション教育の高度化など、技術革新は既に私たちの目の前にあります。課題となっている偏在する医療資源の最適化を図るためにも、これらを現場に実装するための知見を蓄積し、現場と産業界をつなぐ橋渡しの役割を、学会が果たしていくことも必要となると考えています。 さらに私たちは、日本の小児救急の知見と技術をアジア、そして世界へと発信していく必要があります。特に低・中所得国では、公衆衛生の改善に伴って乳幼児死亡率が低下しており、感染症等で命を落としていたこどもたちが生きながらえることができるようになり、その結果、こどもたちが救急医療を必要とする機会が増えています。世界中のこどもたちに、「根拠のある安全かつ安心な救急医療」を提供するために、私たちは諸外国の小児救急医療関係者との連携、国際的な人材交流、標準化された診療プロトコールの共有などを通じて、グローバルな視点で、こどもたちの命を守るネットワークの構築にも挑戦したいと考えています。
これらを実現するためには、学会員の連携、そして学会外との連携も重要です。本学会は、小児救急医だけでなく、外科や集中治療、麻酔科を専門とするさまざまな専門分野の医師が参加しておられます。それだけでなく看護師、救急隊員、行政職の方も加わってくださっています。このような貴重な人材と連携し、さらに保護者、そして地域社会とともに、「こどもを守る社会システム」を構築する協働の場であるべきであると考えています。この学会に集う一人ひとりの知恵と情熱が、次世代の小児医療を支える柱となります。
私たちが目指すべきは、現状維持ではありません。今こそ、私たちは未来を創る主体者として、日本のすべてのこどもたちに、「根拠のある安全かつ安心な救急医療」を届けるために積極的に行動を起こす必要があります。皆さまとともに、変化を恐れず、未来志向で、こどもたちの笑顔を守るために前に進んでまいります。
どうぞ、今後ともご指導・ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。
2025年7月 日本小児救急医学会 理事長 井上信明
2025年 新年の挨拶~年頭所感~
学会員の皆様、今年もよろしくお願いします。元日の能登半島地震で幕を開けた2024年は世界的な異常気象と自然災害、国内外の政情不安、流動型犯罪グループ(トクリュウ)による強盗・詐欺事件の頻発、止まらない少子化、医師偏在・医療経営逼迫に伴う問題の顕在化など、とんでもない波乱の1年でしたが、2025年の年明け(少なくとも正月の3日間)はとりあえず国内で大きな災害、事件は起こらなかったようで、ほっとしています。会員の皆さん方にとって、曜日の並びから9連休となった年末年始はインフルエンザの流行もあり、例年以上に救急診療に忙殺されたことと思います。大変お疲れ様でした。
昨年のノーベル平和賞は日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)が受賞され、大変うれしい出来事の一つでした。しかし、2022年2月24日のロシアによるウクライナ侵攻からほぼ3年、2023年10月7日のパレスチナ自治区ガザでのイスラエルとパレスチナの戦闘から1年以上が経過しましたが、いまだ収束の兆しさえ見えません。今もなお戦争は続いているどころか、北朝鮮の参戦や中東周辺諸国を見てもむしろ戦火は拡大しています。塩野七生氏によると、2000年前に地中海全域を含む大帝国を築いた古代ローマ帝国は従属した国や地域に根付く信仰や慣習の継続を認めたそうです。つまり、いったん戦いが終われば、勝った方が負けた方に譲ることにより安定した社会を作り上げていったということで、世界中が古代ローマの「寛容」の精神に思いを致すことを強く望むばかりです。平和なくして国民の医療は成り立ちません。
わが国では昨年の4月から医師の働き方改革が制度として開始されました。小児救急医療体制の維持にご苦労されている施設も少なくないことと推察します。もちろん、医師を含めて労働者への過重労働の強制が許されないことはいうまでもありませんが、一方で多くの経験と知識を積んで病気の子どもやその家族のために最善の医療を尽くそうという医療従事者の意欲に上限を設けかねない可能性も否定はできません。さらに、この制度を語る時によく登場するのは、「上司の指示による業務ではない」という意味で用いられる「自己研鑽」という言葉です。しかし、この場合の「自己研鑽」には時間外労働をマスクするための方便というニュアンスがどこかに付きまとう感が拭えません。そして、これを含む全体的に"危うい感じ"というのは、医療提供体制の抜本的な整備なしに、この制度だけを導入しようとしたことも一因ではないかと考えます。例えば、ドイツでは病院の設立に州の許可が必要なので、心臓血管外科の手術ができる病院の数は人口100万人あたり1か所とコントロールされており、その結果として医療従事者の集約化と分業体制の実現が可能となり、医師の実働時間は厳守できているそうです。子どもと保護者に寄り添うことが不可欠の小児救急医療をそれと同列に論じることはできませんが、少なくとも国が主導して早急に医療体制の再編に取り組む必要があると思われます。
中世ヨーロッパの貴族社会を支えた道徳観(徳と善意を重視)に端を発し、イギリスのジェントルマンシップにもつながる考え方として「ノブレス・オブリージュ(高貴なるものの責務:Noblesse oblige)」が挙げられます(君塚直隆.貴族と何か、2023)。「ノブレス・オブリージュ」は貴族や上流階級などの財産・権力・地位を持つ者はそれ相応の社会的責任や義務を負うことを意味し、第一次世界大戦下のイギリスでは「ノブレス・オブリージュ」の精神が根づいていたため、国の危急存亡の危機に際して多くの上流階級の子弟が志願して戦地に赴きました。その結果、イギリスは何とか勝利を手にしましたが、国全体の戦死者は8人に1人の割合であったのに対して上流階級の子弟は5人に1人が命を失ったとされています。彼らはまさに命と引き換えに高貴なるものの責務を果たしたといえます。ドイツの哲学者カントは「他者に共感し、他者の幸せのために尽くすことが、自分の幸せにつながる」と述べ、作家の開高 健は「位高ければ、務め多し」と記しています。「自己研鑽」が字義通りに評価され、自らの「自己研鑽」を医師が誇りをもって申告できるような世の中になって欲しいと願っています。
2024年 新年の挨拶~年頭所感~
学会員の皆様、今年もよろしくお願いします。まずは、新年早々に発生した令和6年能登半島地震で亡くなられた方にお悔やみ申し上げるとともに、被災された方々にお見舞い申し上げます。また、この年末年始も例年同様救急診療に忙殺された会員の皆さん方は大変お疲れ様でした。
2023年は新型コロナウイルスパンデミックもようやく収束し、ことスポーツ界に関しては日本のWBC優勝で始まり、男子バレー・バスケットのパリ五輪出場決定、阪神タイガース38年ぶりの日本一、森保ジャパン国際Aマッチ8連勝、大谷翔平2度目の満票MVPとスポーツ史上最高額でのドジャース移籍、藤井聡太8冠達成、イクイノックスG16連勝とレイティング世界1位獲得、武豊&ドウデュース有馬記念で復活、井上尚弥史上2人目の2階級4団体統一など心躍る1年でした。しかし、それ以外の世の中の動向となると、国内では市川猿之助・日大・旧統一教会・旧ジャニーズ・宝塚事件、特殊詐欺被害・広域連続強盗、円安・物価高騰、岸田政権支持率低迷、自民党裏金疑惑など暗い話題ばかりが続き、国外でもウクライナ、ガザでは戦争が長期化して子どもを含む多くの市民が犠牲となり、世界的な気象異常も重なって陰鬱な1年でした。そして、年が明けても解決の方向性はなかなか見えず、急速な少子化と医師の働き方改革に直面して混迷はさらに深まるばかりです。
さて、現在の私の勤務先である京都市子ども保健医療相談・事故防止センター(京あんしんこども館)では、隣接する京都第二赤十字病院小児科と京都市教育委員会の協力を得て、昨年度から小学校高学年(5、6年生)を対象に心肺蘇生法講習会を開催しています。この講習会では、命の大切さと助け合いの精神をテーマにした講義とそれに続く実技講習を「社会見学」の90分間授業としてクラス単位(約30名/回)で実施しています。受講する生徒たちは誰一人居眠りすることなく私の講義を聞き、その後実に熱心に実技に取り組む姿勢に毎回感心させられています。その熱心さはインストラクターとして参加した初期研修医が「自分から積極的に参加する子どもたちの姿勢を見習いたいと思いました」と感想をもらす程です。18世紀にフランスで活躍したジャン=ジャック・ルソーは「子どもは小さな大人ではない」という概念を最初に提唱した人で、その著書「エミール」の中で「人間は生まれながらにして善なる存在で、教育によって子どもの正しい成長を促す必要があり、大人として完成させなければいけない」と指摘していますが、心肺蘇生講習に真摯に取り組む小学生を見ているとまさに“人間の本源的善性(自然の善性)”を実感させられます。
さらに、「教育」は個人の成長だけではなく、社会や組織の発展にも極めて重要です。150年以上前の話になりますが、明治維新により天皇陛下とともに首都や多くの会社の本社機能が一斉に東京に移転したため、京都は人口が2/3に減少して一地方都市に埋没する危機に晒されました。そんな時に京都が講じた主な地盤沈下対策は以下の2つです。1つは教育振興による人材育成で、京都には全国で初めて小学校が開設され、大学の誘致も積極的に行われました。もう1つは琵琶湖疎水の建設で、これにより蹴上に日本初の営業用水力発電所ができ、市電が走り、電灯が灯るようになりました。このようにして京都は10年後には復興を果たすわけですが、それを可能にしたのはまさに“未来への投資”ではなかったかと考えられます。
そして、医療を取り巻く状況が急激に変化している現在、小児救急医療の現場でも是非見習わなければならないのは、前述した教育に関する理念ではないでしょうか。山本五十六連合艦隊司令長官の残した言葉に、「やってみせ 言って聞かせて させてみて ほめてやらねば 人は動かじ」があります。これは上杉鷹山の「してみせて 言って聞かせて させてみる」に影響をうけたとされていますが、次世代を育成するにあたり心すべき格言と思われます。当学会でもこの精神を具現化するべく、昨年は小児救急標準テキストbasic編(中央医学社)を刊行しましたが、今年度はadvance編の発刊に向けて取り組んでいきたいと考えています。
会員の皆様には今後も引き続き、当学会の活動へのご理解とご支援をどうぞよろしくお願いします。
2023年 新年の挨拶~年頭所感~
新年明けましておめでとうございます。2020年初めから始まった新型コロナウイルスパンデミックも丸3年が過ぎようとしていますが、飽きることなく医療逼迫を繰り返し、第8波の途中にあたるこの年末年始も診療に忙殺された会員の方も少なくなかったのではないかと推察します。
さらに、ロシアによる大義なきウクライナ侵攻の長期化に伴う沈鬱ムードの中で、2022年の掉尾を席巻したのはカタールのサッカーワールドカップにおける日本代表の驚異的な勝負強さでした。この歴史的快挙には“真の流行語大賞”は「ブラボー」との意見も多いようです。私の場合、以前は当直と日本代表戦が重なった時はここぞというタイミングで救急室から呼ばれ、当直室に戻ってくると知らない間に逆転したり、されたりしているということが度々ありましたが、今回のワールドカップは日本が得点する時もされる時もlive観戦ができました。
少なくともグループステージに限れば、日本ほど5人の交代枠を有効活用した国はありませんでした。中3日の連戦の中、体力的なハンディも乗り越えた選手交代によりドイツ、スペインに逆転勝利した日本代表の優秀なマネージメントには我々も見習う点が多いと感じました。折しも、2024年4月からは罰則付きの時間外労働規制がスタートする訳ですが、医師の働き方改革もチーム医療の質を落とさない形でのターンオーバーが求められるという点では共通するものがあります。そして、質を担保したチーム医療の実現にあたっては、チームの一員が個々の能力を高めることが何よりも重要で、その際にまず求められるのは各自の自己研鑽への取り組みです。働き方改革の目的は単に勤務時間を減らすというものではなく、勤務時間外に各自が自己研鑽に励んだ結果として、勤務時間中の労働効率がより高まることにより、最終的に良質な医療レベルを達成することにあると思われます。ただし、ワールドカップの場合は登録メンバーの増員が前提の話であり、この点は小児救急医療とすべて同じという訳にはいかないという問題も残ります。
一方、逆説的ですが、私が個人的に感銘を受けたのは37歳という高齢であるにもかかわらず、ほぼ交代なしで全7試合を走り続けたクロアチア主将ルカ・モドリッチの奮闘です。「クロアチアの宝石」とも称されるモドリッチの献身的な走りは‘90年代のユーゴ紛争を経て独立した人口410万人の小国クロアチアの歴史が背景にあり、彼は「祖国を代表し、国歌を聴き、ユニフォームを着ることには測り知れない幸せと誇りを感じている。最後まで勝負を諦めない理由は最も困難な時ほど僕たちは一番強くなれるからだ。」と答えています。2022年8月に亡くなられた京セラ創業者の稲盛和夫氏も「よりよい仕事をするためには自分のためではなく、世のため人のために尽くすという思い(利他の心)が必要で、自己犠牲を伴わない成功はない」と説き、20世紀初頭のイギリスの思想家ジェームズ・アレンの「もし成功を願うならば、それ相当の自己犠牲を払わなくてはなりません。大きな成功を願うならば大きな自己犠牲を、この上なく大きな成功を願うならば、この上なく大きな自己犠牲を払わなくてはならないのです。」という言葉を紹介しています。稲盛氏は自身の子ども達の学校行事に一切参加できなかったことに対して長い間申し訳なかったという忸怩たる思いを抱えていたのですが、ジェームズ・アレンの言葉に出会って救われた思いがしたと述懐しています。翻って、私達も小児医療を志した原点を思い起こしてみると、子ども達と保護者の笑顔と安心のためにという思いがあるからこそ小児救急医療に情熱と努力を注いでこれたのは実はそれほど不思議なことではないのかもしれません。
2022年 新年の挨拶~年頭所感~
新年明けましておめでとうございます。コロナ禍も2年近くが経過し、社会情勢も生活様式もすっかり変わってしまった感がありますが、会員の皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。
新型コロナウイルスによる影響は小児医療に関しても例外ではなく、感染防止対策の徹底により感染症と重症事故・外傷は減少したものの、それは集団免疫の低下や子どもの活動抑制の裏返しでもあり、さらには受診抑制による早期発見の遅れ、団体行動や共同体験の減少によるコミュニケーション能力養成の阻害、虐待や自殺の増加などをもたらすことになりました。コロナ以前から既に少子高齢化が急速に進行中であったわが国における子どもを取り巻く環境の変化スピードは想像以上で、コロナ終息後も元通りには戻らないことを前提として我々が今後果たすことができる具体的な役割について一人一人がそれぞれの置かれた立場で改めて問い直す必要があるのではないかと感じています。
一方で、救急診療を通じて小児と保護者に携わる医療者が目指すべき活動目標はいつの時代も不変で、①エビデンスに基づく医療を実践するための自己研鑽、②子どもと向き合い、保護者に寄り添って患者との信頼関係を構築する、という2つのミッションだと考えています。①のミッションは本来不確実性を有する医療を安心・安全かつ水準以上のレベルで実践するためには欠かすことができません。②については、子どもの全身状態を正確に知るためには子どもと正面から向き合うことが必要で、特に目つきや顔つきを側面から的確に把握することは困難です。これに対して、保護者には正面から向き合うというよりも、まずは横に寄り添うことが大事で、保護者と同じ視点から子どもを見ることが保護者の思いを理解し、共感することに役立ちます。この立ち位置を意識することが子ども、保護者、医療者相互の信頼関係の構築につながるのだと思います。そして、上記2つのミッションを両立させることで、個々の患者に応じたテイラーメイド医療は初めて可能になるのではないでしょうか。さらに、多職種メンバー間でこの活動目標を共有することは小児救急医療チームとしての臨床的洞察力を高め、治療結果の如何を問わず患者が納得できる医療の実現に重要と考えます。
昨年亡くなった人間国宝の落語家である柳家小三治師匠は「落語には台本がない。師匠らの噺(古典落語)を聞いて少しずつ、少しずつ気に入った特徴を加え、その人自身の噺になる。これね、人生そのものだと思うんです。」と指摘されましたが、これは医療にも共通することで、医師の数だけ、患者の数だけ治療内容・転帰にもvariationがあり、その微妙な差異はむしろ個性(匙加減)として尊重されるべきでしょう。しかし、それはあくまでもこれまでに築き上げられた基本(しっかりした土台)があってこその多様性であり、医療においても同様に「師匠らの噺(古典落語)」に相当する基本は不可です。日本小児救急医学会では小児救急医療の教育・研修目標を2020年に発表しましたが、現在はその実践マニュアルとして「小児救急標準テキスト」を本年の学術集会時(2022年7月)の発行を目指して鋭意作成中です。上記テキストに基づく標準医療を学んだ将来の小児救急専門医達がさらに進化・発展させていく小児救急医療の未来に夢を託して新年の挨拶とさせていただきます。
子ども達と保護者に寄り添った支援を使命とする日本小児救急医学会の活動への会員の皆様のさらなるご理解とご支援をお願いするとともに、皆様にとって2022年が良き年となりますよう心から祈念申し上げます。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
2021年 新年の挨拶~年頭所感~
ウイズコロナ時代の年明けを迎え、会員の皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。2020年はCOVID-19対応で明け暮れた1年といっても過言ではなく、医療提供体制、医療経営、さらには医療従事者のメンタルヘルスまでが逼迫される状況が続き、コロナとの共存を目指す指針も定まらない中でひたすら自粛を求められる時間だけが過ぎていくような1年でした。
さらに、わが国では出生数が2019年(約86万5千人)まで5年連続で過去最少を更新してきましたが、2020年は84万人台半ばに減少する見通しとなり、コロナ感染拡大の影響が大きく反映される2021年の出生数は70万人台まで落ち込むことが懸念されています。この急激な少子化は今後の小児医療政策、地域医療構想の見直しにも影響を与えることになり、仮にコロナウイルスが弱毒化して普通の風邪のウイルスに変容したとしても以前の状況、ライフスタイルに後戻りはできないことが危惧されます。
しかし、少子化が進んでも子どもが生まれてくる限り小児医療は必要なものであり、むしろ子どもを健全に育てる重要性はさらに高まります。そのような時代においては、エビデンスに基づきながら子ども達と保護者に寄り添い、患者から信頼される医療の提供がより求められると思われ、日本小児救急医学会が今まで以上に大きな役割を果たすためには学会としてのさらなる基盤強化が重要と考えています。
当学会では山田至康先生が中心となって2008年3月に「小児救急医療の教育・研修目標」を発表しましたが、その後の小児救急医学の進歩を反映するべく、2019年7月に小児救急医療の教育・研修目標改訂ワーキンググループ(井上信明委員長)を立ち上げて改訂作業にあたってまいりました。その結果、昨年(2020年)には現状に即した国際的評価にも耐えうるコンピテンシー基盤型カリキュラムとして12年ぶりに改訂した教育・研修目標を学会雑誌(2020:19:360-372)や学会HPに発表することができました。今回リニューアルされた教育・研修目標はこれから小児救急医療の専門家を目指す方々にとってはまさに羅針盤というべきものです。
「愛好家」とは自分の興味のあることを詳しく勉強して十分な知識を持っていることを自負している人を指し、自称専門家ともいえます。これに対して「専門家」とはあることに関する知識や経験が豊富であることを自分以外の人から評価されている人のことです。つまり、「専門家」というのはあくまでも他の人から認知されてはじめて成立するものです。当学会においてもこのような教育・研修目標を策定した以上は、次のstageとして小児救急医療の「愛好家」ではなく、「専門家」を養成するために、サブスペシャルティ領域専門医制度構築も視野に入れた活動をさらに進めていかなければならないと感じています。
会員の皆様にはさらなるご支援とご協力を重ねてお願いするとともに、皆様にとって2021年が良い年となりますことを祈念します。
2020年 新年の挨拶~年頭所感~
新年あけましておめでとうございます。令和の時代になってはじめて迎える年明けとなりますが、会員の皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。自然災害、異常気象がもはや想定外とはいえない地球環境の中で、少子高齢化が急速に進むわが国において、子ども達と保護者に寄り添った支援を使命とする日本小児救急医学会が果たすべき役割はさらに大きくなっていることを痛感しております。
さて、昨年を振り返りますと、日本小児救急医学会では学会主催の教育セミナーとして小児救急教育セミナー(計9回)、小児脳死判定セミナー(計9回)、小児医療従事者向け災害研修セミナー(計16回)をそれぞれ教育研修委員会、脳死問題検討委員会、災害対策委員会が中心になって定期的に開催してきました。これらの教育セミナーは今後も会員の卒後教育の充実、学術団体としての学会のquality向上を目指して継続していく予定です。さらに、小児救急医療の教育・研修目標(2008年)、小児救急のストラテジー(2009年)が発行されて10年以上が経過したので、教育研修委員会、将来検討委員会が合同で小児救急医療の教育・研修目標改定WGを立ち上げ、改定に向けての検討が開始されました。また、発表より7年が経過した小児腸重積症ガイドラインの改定作業もガイドライン委員会により開始されました。
大変有難いことに、会員の先生方からは日本小児救急医学会雑誌に貴重な論文を多数投稿いただいています。2018年10月よりオンライン投稿・査読システムを開始し、掲載に要する手続きの簡素化と迅速化を図ってきましたが、編集委員会では投稿規定を遵守した論文受付業務のスピードアップを図るため、投稿作成マニュアルと論文投稿時に使用するテンプレートを現在作成中です。 さらに、電子化委員会、編集員会、広報委員会が連携して、今年からは会員情報をマイページ上で管理するべく準備中であり、将来的には電子ジャーナル化、年会費のオンライン納入も実現したいと考えています。なお、多忙な業務の中で、投稿論文のqualityを高めるべく熱心かつ献身的に査読に取り組んでいただいている多くの先生方にはこの場を借りて改めて感謝申し上げます。
日本小児救急医学会としては、地域に密着した形で家庭の保護者を支援する活動にも力を入れていきたいと考えています。保護者にとって重要なことは子どもの病気を診断することではなく、子どもの緊急性(今受診すべきかどうか)を判断することです。地域密着型家庭内トリアージ推進WGでは、保護者が家庭内で子どもをトリアージするにあたって重要な指標として、①個々の局所症状よりもまず全身状態をみること、②次にその全身状態が時間経過とともにどのように推移していくかを観察すること、の2点を重視しています。そこで、WG委員の施設における先行研究結果に基づき、「急病時の子どもの見方と受診の目安~問診票を使って、どんな時に受診すればいいか判断しよう~」という小冊子を昨年より作成中です。完成後は学会監修のプロダクトとして広報することを計画しており、保護者がこの小冊子を有効活用して適切な救急受診(①緊急を要する状態を見逃さず、必要時は早めに受診して重症化を予防できる、②緊急を要さない状態では子どもの安静を優先して不要の受診は避け、根拠をもった経過観察ができる)を実践できるようになることを願っています。
調査研究委員会では、わが国における小児救急重篤疾患のデータベース構築を目指して2017年1月1日より小児救急重篤疾患登録調査(Japan Registry System for Children with critical disease:JRSC)を開始しました。小児救急診療の重症患者は頻度がまれで、単独施設における自験症例のデータのみで該当疾患の全体的な臨床的特徴を明らかにすることが困難である問題点への対策の一つとして着手した調査研究です。その結果、丸3年を経過した2019年12月27日現在、55施設から計1,184例の情報が登録されました(死亡症例〔CPAの外来死亡を含む〕280例、新たに人工換気療法を実施した症例984例、化膿性髄膜炎症例37例、新たに虐待が疑われた入院症例91例で、重複あり)。この中で、特に登録症例数が多かった死亡症例、人工換気療法実施症例については、日本小児科学会と合同2次調査を実施予定です。これらの研究結果により本来予防可能であった小児死亡を減らす対策や人工換気療法実施症例の長期予後が改善するような提言を検討することが本委員会の目標です。JRSCは5年間の予定ですが、途中からの参加も大歓迎ですので、できるだけ多くの施設からのご協力をお願いします。
小児救急SI(special interest)メンバー制度が2017年12月10日から開始され、これまでに173名の会員が認定されました。この制度は学会の活動に一定基準以上参加し、小児救急患者に強い興味(special interest)をもって診療にあたり、小児救急医療の学術的発展と普及に貢献している医療従事者を本学会が独自に認定する制度です。小児救急SIメンバー資格を希望される会員は毎年9月1日~10月末日に申請書類を提出することになっており、小児救急SIメンバーには認定書、メンバーカード、ピンバッジが送られます。2019年度の申請受付は終了しましたが、有資格者は今秋に是非申請してください。
おそらくどなたにでも人生の師匠と仰ぐべき指導者は複数おられると思いますし、教育・薫陶を通じた価値観の共有こそがみんなのベクトルを同じ方向に向けて組織を維持、発展させることにつながると考えます。先輩から色々と教えてもらったことを感謝する後輩は自身の後輩にも熱心な指導を行い、その継承により伝統は守られていきます。しかし、不幸にして先輩から色々なことを教えてもらえなかった後輩は自身の後輩の指導にも消極的になり、組織のactivityは結果として衰退していくことになるのではないでしょうか。改革・改善はしっかりした土台があってはじめて成功するといえるのであり、日本小児救急医学会の今後の発展を想うと、「教育」、「育成」、「指導」の気持ちを忘れてはならないと私は考えています。
最後に、「少子高齢化時代の子育て支援を応援する学会」として今後も日本小児救急医学会の活動を多面的に発展させていきたいと考えています。会員の皆様にはさらなるご支援とご協力を重ねてお願いするとともに、皆様にとって良い年となりますことをお祈り申し上げます。
2019年 新年の挨拶~年頭所感~
会員の皆様、新年あけましておめでとうございます。
2018年の世相を表す「今年の漢字」に「災」が選ばれたように、昨年は2月の北陸地方での豪雪、夏季の異常な熱暑に加え、6月の大阪北部地震、7月の西日本豪雨、9月の台風21号、北海道胆振東部地震と度重なる自然の脅威に翻弄される1年でした。さらに、10月11日には前理事長の市川光太郎先生がご逝去され、当学会にとっては忘れることのできない平成最後の年になってしまいました。人生は全く不公平なものであり、人間は限りのある儚い存在であり、そして災害・事故は反復するという事実を改めて痛感するとともに、元号の改定という歴史の転換期を迎えて、鎮魂の思いからの時代の再生を願わずにはおれません。
さて、昨年を振り返りますと、日本小児救急医学会にとって災害救護は大きな活動分野の一つであることはいうまでもありませんが、災害が発生した時に十分に機能するためには平時からの準備が不可欠といえます。その意味で、災害医療委員会が開催する「小児医療従事者向け災害研修セミナー」は他学会からの開催依頼も多くあり、開催回数は2018年12月までに計11回に達しています。また、東日本大震災継続支援も「ほそくながく」継続中です。さらに、学会主催の教育セミナーである小児救急教育セミナー(計9回)、小児脳死判定セミナー(計8回)についても今後も継続開催していく予定です。
最近の日本小児救急医学会雑誌への投稿論文の増加はまさに右肩上がりで、ページ数の増加を実感されている会員の方も多いと思います。学会雑誌の掲載論文の増加は当学会が学術団体としても精力的に活動していることの表れであり、誇るべきことですが、それに伴う印刷代・郵送費の増加も看過できず、昨年10月より投稿規定を変更してオンライン投稿・査読システムを開始しました。多くの投稿論文に対して、論文のqualityを高めるべく、熱心かつ献身的に査読に協力していただいた先生方にはこの場を借りて改めて感謝申し上げます。
小児救急SI(special interest)メンバー制度が2017年12月10日から開始され、昨年2月には初年度として2002年度以前の入会者145名が認定されました。小児救急SIメンバー資格を希望される会員は毎年9月1日~10月末日に申請書類を提出することになっています。小児救急SIメンバーには認定書、メンバーカード、ピンバッジが送られますので、有資格者は是非申請していただき、学術集会にはピンバッジを付けて参加しましょう。
調査研究委員会ではわが国における小児救急重篤疾患のデータベース構築を目指して2017年1月1日より小児救急重篤疾患登録調査(Japan Registry System for Children with critical disease:JRSC)を開始しました。ちょうど2年が経過した2018年12月27日現在、48施設から822例の情報が登録されています(死亡症例〔CPAの外来死亡を含む〕179例、新たに人工換気療法を実施した症例682例、化膿性髄膜炎症例24例、新たに虐待が疑われた入院症例75例で、重複あり)。この中で、特に登録症例数が多かった死亡症例、人工換気療法実施症例については、日本小児科学会と合同(前者は子どもの死亡登録・検証委員会、後者は小児救急委員会)で2次調査を今春から開始する予定です。JRSCは5年間の予定ですが、途中からの参加も歓迎で、今後日本小児科学会との合同調査によりさらに症例数が増加するとともにより詳細な分析結果が情報提供できるのではないかと期待しています。
カナダの内科医であるウイリアム・オスラー博士の言葉に「医学は不確実性の科学であり、可能性の芸術である」の一節があります。これは不確実であるが故にエビデンスに基づく標準化医療を追及しなければいけないという戒めとともに、患者の個体差を配慮して個々の患者に寄り添う医療者の感性(アート)を尊重する心を忘れてはならないという医学の基本を示す洞察です。自分の状態を自身の言葉で正確に伝えられない子どもを診療対象とする小児医療においては常に座右の銘としたい言葉であり、医療の問題点を科学的に分析していく緻密な視点と患者・保護者に寄り添って支える育児支援の視点を両立させる診療こそ小児救急医療の魅力であり、原点であると私は考えています。
平成とともに逝かれた市川光太郎先生のご遺志を継承し、日本小児救急医学会は「少子高齢化時代の子育て支援を応援する学会」として今後も活動を多面的に発展させていきたいと思っています。会員の皆様にはさらなるご支援とご協力をお願いするとともに、皆様のこの1年のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。
日本小児救急医学会理事長就任の挨拶
この度日本小児救急医学会理事長を拝命いたしましたので、ご挨拶申し上げます。計17年間にわたり本学会を牽引していただき、本学会の代名詞というべき市川光太郎先生の後任ということで、双肩にかかる重責は言葉に尽くせないものがありますが、微力ながら尽力する所存ですので会員の皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。
私の京都第二赤十字病院における恩師である水田隆三先生が本学会の創設メンバーの一人であった縁で、私自身も25年以上本学会にお世話になってきました。そして、市川前理事長をはじめ多くの先生からご指導いただいたことは、「本学会の会員は小児科、小児外科、麻酔・集中治療科、救急科、脳外科、整形外科、形成外科、看護師、救急隊員など多領域のメンバーで構成されているが、会員の主要なメンバーは領域を問わず、全国津々浦々の病院あるいは診療所の臨床現場で、昼夜を問わず小児の救急医療に携わっている人々である」ことを忘れてはならないということでした。従って、この学会の存在意義は小児救急診療の現場で頑張る会員の声を汲み上げ、その意見を代表する団体であるという点にあると私は考えています。
小児救急医療は1次から3次まで、内因性から外因性まで、あるいは急性疾患から慢性疾患・在宅障碍児の急性増悪までというように幅広い領域が対象になるだけではなく、医療提供体制にも地方から都市まで厳然たる地域差が存在します。しかし、我々の立場は小児の医療に救急という切り口で関与するという意味で共通しています。そして、そもそも小児の医療とは子どもに向き合い、保護者に寄り添うものでなければならず、子どもは保護者に育てられて大人に成長していくものですが、保護者の子育てにおける最大の不安は子どもの急病とケガであるということを考えると、子育て支援の推進にあたって小児救急医学会が果たすべき役割は極めて大きいと思われます。つまり、本学会は「少子高齢化時代の子育て支援を応援する学会」でありたいと私は考えています。
その上で、一次救急については小児科医会と連携して#8000および家庭看護力の向上を目指し、小児科学会とも連携して小児救急初期対応コースであるJPLSコースの普及に協力したいと思っています。また、1歳以上の死亡数が悪性新生物とほぼ同数の事故死亡を減少させるための子どもの事故防止対策は喫緊の重要課題です。一方、2次、3次救急については小児救急医が過労状態に陥らないような医療体制の確立が必要で、国や自治体など行政と連携して集約化、広域化により重篤小児に対する救急医療体制の整備が不可欠です。そのためには、それぞれの地域における重篤小児の実態調査結果に基づいて優先度を決め、地域ごとに最善の対応策を具体的に考えていくことが重要であると思っています。さらに、少子化の進行に逆行する虐待件数の増加に対しては日本子ども虐待学会との連携を、乳幼児の突然死の検証を含めたchild death reviewの推進には日本SIDS・乳幼児突然死予防学会との連携を、効果的な災害医療の推進には日本小児科学会との連携を進めていきたいと考えています。
従来の大学の医学部教育ではややもすれば軽視されがちであった小児救急医学の学問的体系化も今後の本学会に残された大きな課題であると認識しています。そのためには、小児救急重篤症例登録調査を通じたデータベースの整備、学会発のガイドラインの充実と改訂、教育コース(小児救急教育セミナー、小児脳死判定セミナー、災害医療研修会)の普及と新しい医療技術の導入、学会が監修する「ケースシナリオに学ぶ小児救急のストラテジー」の改訂と小児救急認定医制度の確立などが今後の具体的な活動目標となってくると考えており、そのための委員会活動の活性化を支援していきたいと考えています。
最後に、日本小児救急医学会の使命は医療としての問題点を細かく分析していく緻密な視点と、保護者の気持ちに寄り添って支えるという育児支援の視点を両立させた活動を推進していくことであり、それこそが小児救急医療の魅力であり、また原点であることを常に忘れずに全力を尽くしたいと考えています。どうか、本学会のさらなる発展のために、会員の先生方のこれまで以上のご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。